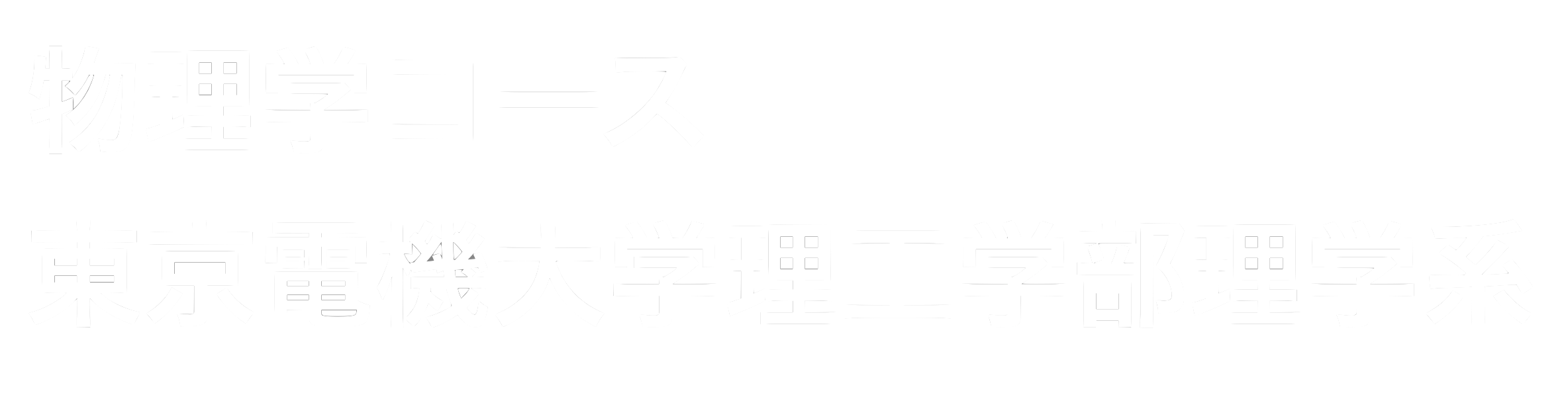第75回講演会 2020年1月8日(水)15:30~17:10
植本 光治 氏 (神戸大学工学部)
光科学の数値実験室
概 要: 物理学では「理論」「実験」といった大分類がありましたが、現代では「計算」という第三の柱が重要な役割を担いつつあります。
光科学においては反射・吸収・集光といった光路計算や、電磁波の散乱や導波路を扱う電磁界計算、「ナノフォトニクス」として注目される極小サイズの光デバイスの設計・解析にも多用されています。さらに最近では、量子力学に基づく電子系の第一原理計算と組み合わせることで、光と物質の相互作用を原子スケールからシミュレーションし、物質のもつ様々な非線形光学特性の予測、さらには新材料探索といった応用も視野に入りつつあります。
こうしたシミュレーションが可能になった背景には、この数十年での計算機資源とソフトウェアの急速な進歩があります。現代のスーパーコンピュータは数十ペタフロップス(毎秒10の16乗回程度の浮動小数点演算性能)が達成され、また、2020年にはこれまでの「京」コンピュータの約100倍の性能を有するポスト京コンピュータ「富岳」が神戸に建造されようとしています。
本講演では、発表者がこれまでポスト京プロジェクトで関わってきた、大規模並列計算機向けプログラム開発について、光科学シミュレーションへの応用研究などの経験について紹介したいと思います。
第74回講演会 2019年10月16日(水)15:30~17:10
落合 勇一 氏 (千葉大学名誉教授)
炭素系材料を用いたデバイスの開発
第73回講演会 2018年12月12日(水)15:30~17:10
井賀 充香 氏 (日本ペイントホールディングス株式会社 R&D本部)
観察・仮説・検証!
新しい塗料の創り方をご紹介します。
概 要: 日本人にとって、塗料は身近で遠い商品です。みなさんが日々目にするものは、何かしら塗装(コーティング)されています。しかし、日常の生活では塗膜を意識されることは少ないでしょう。したがって、塗料会社の研究開発とは一体どんなことをしているの?と思われるのではないでしょうか?
塗料メーカーは、塗料を開発・製造し、お客様に提供しています。塗料は各々の現場にて被塗物に塗装され、塗膜となって「美観と保護」という機能を発現します。したがって、塗膜性能はもちろん、塗料としての安定性や塗装してから塗膜を形成するまでの工程での使いやすさ(「塗装作業性」と言います)を最適化しています。すなわち、塗料の安定性、作業性、塗膜性能を3つが塗料の要件なのです。私の所属するR&Dでは、新しい技術を塗膜にいち早く取り込み、かつ、3要件を満たす塗料を開発するための研究開発を行っています。私は基盤技術の「塗装作業性」について課題を解決し、より優れた塗料を提供する物性解析を行っています。その方法は当社で「サイエンティフィックアプローチ」と呼んでいる、3つのステップで行います。まず、原材料から塗料化、塗装、乾燥を経て塗膜に到るまでのすべての工程を詳細に観察して可視化することから始まります。次に問題となっている現象が起こるメカニズムを明らかにします。そして、解決策を提示します。業界で常識とされていることを乗り越え、他社と差別化する技術を創り出すのは簡単ではありません。そこで私は、強い探究心を持って科学的な解明を「やり抜く」ことを意識しています。
また、塗料を開発するということは、対象となる被塗物の産業を理解することであり、塗料を使う地域を理解することであり、未来を考えることです。そのため、理系だから、研究開発だからと言ってそれだけに集中するのではなく、世界・産業・歴史など広い視野を持って仕事ができる、とても面白い仕事です。
今回のお話は、当社の塗料開発と、その中における私の業務について紹介します。もちろん私の話は様々な仕事の中の一例ですけれども、皆さんが企業に就職し、活躍しているイメージを持っていただく参考になれば幸いです。
第72回講演会 2018年6月13日(水)15:30~17:10
安藤 恒也 (東京工業大学 栄誉/名誉教授)
グラフェンと関連物質の物理的興味
概 要: 現在,新しい原子層2次元物質が注目を浴びている.その中で最も典型的な物質がグラフェンであり,炭素原子からなる層状物質グラファイトの1層に対応する.グラフェン上の電子はニュートリノと同じワイル方程式(ディラック方程式の相対論的極限に対応)に従うという著しい特徴をもつ[1-3].そのため,通常の2次元系とは異なる興味深い性質を示す.例えば,反磁性帯磁率のデルタ関数的特異性[4],それと密接に関係したトポロジカル谷ホール効果[5],電気伝導率の特異性と最小伝導率[6]などである.この講演ではこれらの現象を理論的側面から紹介するとともに,磁気抵抗効果についての最近の理論的研究やグラフェン以外の新しい原子層物質についても簡単に触れたい.
Reference
[1] T. Ando, J. Phys. Soc. Jpn. 74, 777, (2005).
[2] A.H. Castro Neto, F. Guinea, N.M. Peres, K.S. Novoselov, and A.K. Geim, Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009).
[3] D.S.L. Abergel, V. Apalkov, J. Berashevich, K. Ziegler, and T. Chakraborty, Adv. Phys. 59, 261 (2010).
[4] M. Koshino and T. Ando, Solid State Commun. 151, 1054 (2011).
[5] T. Ando, J. Phys. Soc. Jpn. 84, 114705 (2015).
[6] N.H. Shon and T. Ando, J. Phys. Soc. Jpn. 67, 2421 (1998).
第71回講演会 2018年5月16日(水)15:30~17:10
村勢 則郎 (元東京電機大学教授)
架橋高分子ゲル中の水の凍結状態 ー氷晶(粒)のサイズ・形状とガラス化の可能性
概 要: セファデックス(架橋デキストラン)ゲル中の水の凍結挙動は架橋密度によって異なることがDSC測定(示差走査熱量測定)により明らかになっている。そして、適度な架橋密度をもつG25ゲル(排除限界分子量:5,000 Da)の場合、含水率が約50%の試料を徐冷しても水は部分的に凍結せずに、昇温過程で氷晶形成する。架橋密度がG25より高くても低くても、このような昇温結晶化は顕著には観測されない。昇温結晶化のメカニズムを解明するには、形成される氷晶(粒)のサイズ・形状を含めて、ゲル網目構造内の水の凍結状態を知る必要がある。 本講演では、主として放射光を用いたX線CTとX線回折による測定結果から、ゲル試料中に形成される氷晶(粒)のサイズ・形状およびガラス化の可能性について議論する。また、氷粒サイズの観測結果と氷の融解開始温度から求まる氷/水和デキストラン間の界面自由エネルギーについても考察したい。
第70回講演会 2017年10月19日(木)15:10~16:40
島田 政信(東京電機大学 理工学部 建築・都市環境学系)
SAR干渉計による地殻や変動の把握
概 要:地球はその長い営みの中で、徐々に形を変えています。超長期的には大陸が移動し、短期的には、地震による地盤の変化、ゆっくりとした地滑り、地下水(工業用水)汲み上げなどによる局所的な地盤沈下、火山活動に伴う火口隆起などが起こっています。 大部分は自然活動に伴って生じますが、中には人間活動によるものもあります。 このような変化を正確に把握することは、地球表面に生活する人類にとって、その現状を 認識したりや将来把握を行ったり、あるいは安心安全の観点から重要です。幸いなことに、今、このような変化を面的にcm単位で捉える技術が実用化の方向にあります。 干渉SAR解析です。生まれたのは、1976年です。干渉SARは、光を用いたヤングの実験「一つの源から出た光を2つのスリットから分けると、スクリーン上で低い縞が現れる現象」(1805)と起源を同じにします。当初は実験室で干渉を行なっていたのですが、1978年に 宇宙機に搭載されるや、徐々に広がり、1991年以降、GPS技術の向上や電子機器の 安定性や精度向上とともに、格段に精度向上を見せてきました。 特に、日本の地震(予知)を議論する気象庁の地震予知連絡会で、使用すべき手法として 採用されているのは周知のことです。本フォーラムでは、このような発展を遂げてきたSAR干渉計の原理、精度、日本での発展、解析事例、長所と短所、そして現状や未来について紹介します。
第69回講演会 2017年7月13日(木)15:10~16:40
玉谷 知裕(産業技術総合研究所)
半導体を用いた高次高調波の発生メカニズム ~高強度光物理の基礎~
概 要:光の周波数を変換する技術は重要な技術であり、すでに我々の社会において
様々なところで使われている。高次高調波発生はその中でも注目されている技術の
一つであり、特に原子分子気体を用いた高次高調波発生は紫外からX線領域における
アト秒パルス生成の有用性から、現在まで盛んに研究が成されて来た。
近年、 高強度THz光の発生が可能となり、半導体を初めとする凝縮系を用いた
高次高調波発生が注目されている[1]。これはTHz光における光子エネルギーが
半導体の典型的なバンドギャップエネルギーと比較して非常に小さく、さらに安定した
電場波形を形成できることから高次高調波発生に対する高効率な制御が
実現できると期待されるためである。しかしながら、このような実験的進歩にも関わらず
高強度THz光照射下での凝縮系における高次高調波発生のメカニズムは明らかに
なっていない。以上の状況を踏まえ,本講演では, 半導体に高強度THz光を
照射した際のキャリアダイナミクスの定性的な理解の仕方を示し、それによって生じる
高次高調波発生のメカニズムを明らかにする[2, 3]. さらにそれらを踏まえ、
グラフェン[4]や遷移金属ダイカルコゲナイド[5]における高次高調波の特異な
性質を説明する。
Reference
[1] O. Schubert et al., Nature Photon. 8, 119-123 (2014).
[2] T. Tamaya, A. Ishikawa, T. Ogawa, and K. Tanaka, Phys. Rev. Lett. 116, 016601 (2016).
[3] T. Tamaya, A. Ishikawa, T. Ogawa, and K. Tanaka, Phys. Rev. B 94, 241107(R) (2016).
[4] N. Yoshikawa, T. Tamaya, and K. Tanaka, Science 356, 736 (2017).
[5] T. Tamaya, S. Konabe, and S. Kawabata, arXiv:1706.00548.
第68回講演会 2017年6月8日(木)15:10~16:40
川畑史郎(産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門)
量子コンピュータと量子アニーリング入門 基礎から最先端まで
概 要:最近、新聞やWebなどの様々な媒体で量子コンピュータや量子アニーリングといった キーワードが世間を賑わしている。量子コンピュータと量子アニーリングマシンは、 量子力学原理を積極的に利用した計算機である。つい数年前まで、これらが 商用化するのは遠い遠い未来の話と思われていた。ところが、2011年にカナダの ベンチャー企業D-Wave Systemsが「量子アニーリングマシン」を製品化し、 2013 年にGoogle、NASA、ロッキード・マーティンに販売した。つまり量子力学原理に 基づく計算機は既に商用化されているのである。量子アニーリングは、量子揺らぎを 制御することによって組合せ最適化問題を解く手法であり、東工大の西森教授によって 1998年に提唱された。組合せ最適化問題は、農業、創薬、人工知能、金融、製造、 運輸、教育等のありとあらゆる産業分野において現れる。そのためD-Wave Systemsによる 商用化以降、世界の名だたる企業がこの分野にぞくぞくと参入するようになってきた。 それに対し、量子コンピュータは汎用コンピュータの一種である。量子コンピュータを 用いることで因数分解問題、機械学習、量子化学計算などが高速に解けることが理論的に 示されている。そのためGoogle、マイクロソフト、インテル、IBMなどの世界的大企業が その商用化に向けた研究開発を行っている。本講演においては、量子コンピュータや 量子アニーリングの基礎から最新の研究・ビジネス展開までできるだけ平易に解説を行う。 さらに産総研がすすめている超伝導量子アニーリングマシンの研究開発(NEDO)ついても 紹介を行う。
第67回講演会 2016年5月18日(木)15:10~16:40
根本 航 准教授 (生命理工学系)
環境中からの生物情報収集基盤の構築
概 要:生物を形作る情報の多くはゲノム配列上にコードされている。近年の 技術革新により核酸配列解読コストが劇的に低下したことで、大量の 核酸配列解読を短時間で行うことが可能になった。この技術は捕獲・培養が 困難な生物に由来する莫大な量の核酸配列情報を、環境中から収集して 解読し尽くすことにも応用されている。その結果、どこにどのような生物が どのくらい棲息しているかを見積もることができつつある。国内では、 バイオインフォマティクスコミュニティーが中心となって、ソメイヨシノの花びらに 棲息する微生物由来の配列情報を収集する、お花見メタゲノムプロジェクトが 開催された。本セミナーではまず、我々も参加したこのプロジェクトを簡単に 紹介しつつ、環境中から生物情報を収集する際の問題点についてお話しする。 次に、この問題点の克服を目指して、我々が開発を進めている、環境中から 生物情報を収集するためのアプリケーション、MappEnvについて紹介する。
第66回講演会 2016年4月27日(木)15:10~16:40
中井 正則 教授 (建築・都市環境学系)
波を流れで制御する
概 要:浅海域の高波抑制は,土木工学上の重要な研究課題であります.
この問題に対して,従来から,各種の防波堤を用いた対策がとられてきました.
本研究は,従来の方法とは異なる視点より,流れを与えることによって
高波を抑制しようとするものであります.この方法は,簡易的かつ環境負荷の
小さいものであり,将来性・応用性の点で優れたものと考えられます.
なお,この方法の活用により,高波抑制のみならず,浅海域の水質改善をも
期待できます.
第65回講演会 2016年12月15日(木)15:10~16:40
平野 太一 氏 (東京大学生産技術研究所)
インクジェットを科学する
概 要:インクジェット技術は今や、単なる印刷手法に止まらず、薄膜の 生成や生体疑似細胞の合成などにも利用され、学術領域の拡大あるいは産業応用における 効率向上に役立っている。本講演では、このインクジェット技術に凝集された様々な要素を 科学的に考えてみよう!を合い言葉に、微小液滴の物性、液滴射出技術、飛翔液滴の空中制御法などを やさしく解説する。また、所属研究室で独自に開発された最新のインクジェット技術について、 開発秘話や苦労話を交えながら紹介したい。
第64回講演会 2016年11月24日(木)15:10~16:40
長尾 雅則 氏 (山梨大学 クリスタル科学研究センター)
多元素系超伝導体の単結晶育成とその評価
概 要:電気抵抗がゼロになる超伝導は, 学術的にも応用面でも興味深い現象である.
その中でも, 超伝導転移温度が液体窒素の沸点(77K)を初めて超えた銅酸化物
超伝導体[1]や2008年に発見された鉄系超伝導体[2]は, 盛んに研究が行われている.
物質を研究する上で, その物質が持っている真の性質をあきらかにするには,
単結晶が必要となる. しかし, これらの物質は, 4元素以上で構成される多元素系
化合物であるため, 一般的に単結晶の育成が難しい.
本講演では, 銅酸化物超伝導体の針状単結晶(ウィスカー)と鉄系超伝導体の
類似物質であるBiS2系超伝導体[3]単結晶の育成について述べるとともに,
それを用いて行った超伝導特性の評価について紹介したいと思う. また, これらの
単結晶育成には, フラックス法と呼ばれる方法が用いられており, 単結晶育成に
関する“溶かす”と“融かす”の違いについても紹介したいと思います.
参考文献:
[1] M. K. Wu, et al. Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 908.
[2] Y. Kamihara, et al. J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 3296.
[3] Y. Mizuguchi, et al. J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 114725.
第63回講演会 2016年7月14日(木)15:10~16:40
松浦 有祐 氏 (東京大学 生産技術研究所)
粘弾性計測法について考える
概 要:実験系の研究では計測がつきものです。市販の装置を用いて測定や評価をし、
従来と違った結果が得られればそこに希望を見出して先に進める、というのが主な
プロセスだと思います。しかしながら、計測装置が提供してくれる測定結果は本当に
正しいものでしょうか。
本講演では粘性、弾性に注目して話をします。粘性の計測といっても色々な
手法があり、それぞれ得意、不得意な領域が存在します。得られた結果から
正しい議論を行うためには手法の特性をよく知る必要があります。
そのような測定法の事情について真面目に考えてみたいと思います。
第62回講演会 2016年5月26日(木)15:10~16:40
中根 茂行 氏 (国立研究開発法人 物質・材料研究機構)
新機能の創出を目指した遷移金属酸化物の結晶構造制御
概 要:機能性材料は、一般的に、光や電磁場、熱といった刺激(input)に対する応答機能(output)が
要求される材料であり、電子デバイスや光学素子、磁性材料、触媒、分離膜など、様々な分野で
精力的に応用研究が行われている。特に近年は、機能性材料を活用するシステムが、複雑・精密・
高機能化しており、材料に要求される機能も多様化している。こうした潮流の中では、材料が有する
本質的な物性に迫る基礎研究も、界面や表面、欠損など、従来の研究が重視してこなかった
非連続性や対称性を有する局所領域や特殊相に注目するようになった。
本講演では、遷移金属酸化物に関する物性研究を行ってきた講演者が、自身の研究を通して
注目するTiO2系化合物の特殊相やスピネル型酸化物の特殊物性領域について紹介する。
TiO2は、光触媒や太陽光発電、化粧品、各種半導体デバイスなど、非常に幅広く応用され、
研究されている典型的な酸化物半導体である。この物質を議論する上で重要となる特徴は、
まずはその結晶構造にあり、天然に存在するルチル型、アナターゼ型、ブルッカイト型だけでなく、
いくつかの特殊な結晶相の存在が知られている。しかし、一般的なTiO2研究は、作製が容易な
ルチル型とアナターゼ型に限られており、他の構造については、議論が十分に行われていないのが
実情である。そこで本講演では、こうした特殊相の一つであるブロンズ型TiO2について、
その作製方法と期待される物性について紹介したい。
一方、典型的なスピネル型酸化物であるCoAl2O4は、4配位のAサイトに位置する
Co2+のd-d遷移によって鮮やかな青色を呈する。この特徴は、古くから陶磁器などの青色顔料として
利用されてきた。しかし近年、磁性分野でこの物質のCo2+イオンの磁気フラストレーションが注目され、
新たな関心を集めている。本講演では、こうしたスピネル型酸化物から見出された特徴的な
結晶構造変化が磁気特性や光学特性に及ぼす効果について紹介したい。
第61回講演会 2016年4月28日(木)15:10~16:40
安食 博志 氏 (理学系 物理学コース)
共振器中--量子ドット系における量子もつれ光子対生成の理論
概 要:非局所的な量子もつれ状態(量子力学に特有な状態)は、量子鍵配送、量子テレポテーション
などの量子情報処理技術や量子コンピューティングなどの媒体として重要な役割を果たす。
様々な種類の量子もつれ状態のうち、偏光自由度がもつれあった光子対は電子などに比べると
外界との相互作用が非常に小さいので、量子情報伝達の媒体として有望である。
量子もつれ光子対の代表的な発生方法には、非線形光学過程のパラメトリック下方変換がある。
最近では、バルクの半導体の共鳴励起状態を介して、量子もつれ光子対が生成できるようになった[1]。
このような光子対生成は共鳴条件下で起きるので、生成効率が非常に高い。
さらに、量子ドットにおけるカスケード緩和過程(励起子分子→励起子→基底状態)による
量子もつれ状態の生成実験も報告された[2]。量子ドットからの光子対生成では、その生成方向を
絞ったり、生成効率を上げるために共振器を利用することが多い。ただし、これまでは共振器のQ値が
比較的低い場合に限定されていた。一方、フォトニック結晶などを用いた共振器のQ値が
近年めざましく高くなり、共振器中の光子と物質系の相互作用を非常に強くすることができるようになった。
この場合、共振器量子電磁力学に特有なドレスト状態(光子と物質励起状態の重ね合わせ状態)が
形成される。
本講演では、ドレスト状態を介した量子もつれ光子対の生成とその状態、さらに量子もつれ光子対の
純度と生成効率が高くなる条件について理論的な研究を紹介する[3-5]。
参考文献:
[1] K. Edamatsu, G. Oohata, R. Shimizu, and T. Itoh: Nature 431, 167 (2004).
[2] R. Stevenson et al.: Nature 439 (2006) 179. など
[3] H. Ajiki, H. Ishihara, and K. Edamatsu: New J. Phys. 11, 033033 (2009).
[4] K. Shibata and H. Ajiki: Phys. Rev. A 86, 032301 (2012).
[5] K. Shibata and H. Ajiki: Phys. Rev. A 89, 042319 (2014).
第60回講演会 2016年1月14日(木)15:10~16:40
山室 修 氏 (東大物性研)
パラジウム水素化物ナノ粒子の構造とダイナミクス
概 要:パラジウム水素化物は最も代表的な金属水素化物で、水素貯蔵や触媒などの応用的な 興味だけでなく、量子性を有しうる単純な無秩序系として、物性物理の観点からも古くから 注目されてきた。我々はこの数年、パラジウムをナノ粒子化することで物性がどのように 変化するかに注目して、中性子散乱の研究を行っている。バルク状態では水素原子は 面心立方格子の正8面体サイトのみに位置するが、ナノ粒子になると正4面体サイトが 安定化し、水素原子がより高速で移動することを明らかにした。講演では、中性子散乱法の 基礎から始め、水素の研究にいかに中性子散乱が適しているかについても示したい。
第59回特別講演会 2015年12月19日(木)10:30~18:15
小田垣 孝 氏 (理学系 物理学コース)
「鳩山サイエンスフォーラム in 北千住 ー小田垣孝:研究49年の軌跡ー」
プログラム:
・ 10:30 - 10:40 はじめに
・ 10:40 - 11:05 : 鳥飼 正志(三重大工)
「自己組織化の逆問題」
・ 11:05 - 11:30 : 大久保 毅(東大物性研)
「危険なイレレバント場が生み出す二つの長さスケールとスケーリング関係式」
・ 11:30 - 11:55 : 藤江 遼 (東大院法)
「バイリンガル系における言語中立性の安定性条件」
・ 11:55 - 12:20 : 松本 章吾(電機大院先端)
「非平衡転移としての放電現象」
・ 昼休み:12:20 - 13:30
・ 13:30 - 13:55 : 小山 暁 (豊田高専一般)
「高専の物理教育」
・ 13:55 - 14:20 : 吉留 崇 (東北大院工)
「コヒーレントX線イメージング実験データ分類法の研究」
・ 14:20 - 14:45: 尾嶋 拓 (京大エネ理工)
「タンパク質の水和自由エネルギーの高速計算法の開発」
・ 14:45 - 15:10: 浴本 亨 (横浜市立大)
「分子動力学シミュレーションを用いた計算創薬技術の高度化と
タンパク質の溶液構造解析」
・ 休憩:15:10 - 15:30
・ 15:30 - 15:55: 寺田 弥生(東北大金研)
「少数不純物粒子がコロイド一層膜の凝固過程に及ぼす影響」
・ 15:55 - 16:20: 細田 真妃子(東京電機大理工)
「ガラスとEMS」
・ 16:20 - 16:45: 水口 朋子(京工繊大)
「過冷却シクロヘキサンにおける相転移と構造変化」
・ 16:45 - 17:10: 山室 憲子(東京電機大理工)
「生体保護物質グリシンベタインのダイナミクスと水和構造」
・ 休憩:17:10 - 17:30
・ 17:30 - 18:15: 小田垣 孝(東京電機大理工)
「研究49年の軌跡」
・ 懇親会:19:00~
第58回講演会 2015年11月26日(木)15:10~16:40
賀 川 史 敬 氏 (理化学研究所CEMS)
強相関電子系における電荷自由度の結晶化と急冷によるガラス化
概 要:液体は通常、徐冷すると原子(または分子)が規則正しく配列し
た結晶化を起こすが、結晶化が間に合わないほど速く急冷した場
合は、原子は不規則な配列なまま凍結し、いわゆるガ ラス状態
(構造ガラス)を形成する。このよく知られた振る舞いと類似し
た現象が、固体中の強相関電子系についても起こり得ることが、
有機導体θ-(ET)_2Xにおける研究を通じて分かってきた[1,2]。
有機導体θ-(ET)2MM'(SCN)_4 [M = Rb/Cs/Tl; M’ = Zn/Co]は、
低温でウィグナー型の電荷秩序(電荷の“結晶化”)を起こすが、
急冷下では電荷秩序転移を起こすことなく、電荷がガラス的に凍結
するという振る舞いを示す。本講演では、電荷ガラスと構造ガラス
の共通点について概観した上で、“電荷のガラス形成能”[3]及び
それを利用した電荷ガラス/結晶の不揮発な相変化メモリ機能[4]
について紹介したい。
また、急冷を利用した磁気スカーミオン
(電子スピンが渦状に配列した構造)の相制御の研究も併せて紹介
する[5]。
[1] F. Kagawa et al., Nat. Phys. 9, 419 (2013).
[2] T. Sato et al., Phys. Rev. B 89, 121102(R) (2014).
[3] T. Sato et al., J. Phys. Soc. Jpn. 83, 083602 (2014).
[4] H. Oike et al., Phys. Rev. B 91, 041101(R) (2015).
[5] H. Oike et al., Nat. Phys., advance online publication.
第57回講演会 2015年10月29日(木)15:10~16:40
本間 佳哉 氏 (東北大学 金属材料研究所)
ウラン・超ウラン化合物の新奇な低温物性
概 要:ウランと聞けば殆どの人は核分裂で莫大なエネルギーを生み
出す核燃料としてのウランを連想することでしょう。しかし、
ウランさらにはプルトニウムなどの超ウラン元素を含むアク
チノイド化合物の中には、本来仲違いする磁性と超伝導の共
存現象や、通常の双極子より高次の磁気モーメントが整列す
る多極子秩序などが報告され、固体物理学のホットな話題と
なっています。これらの奇妙な性質は、遍歴的な3d電子と局
在的な4f電子の中間的な振る舞いをするアクチノイド元素
の5f電子に由来しています。
講演ではウランや超ウラン元素に馴染みのない方々を想定
して、まずはアクチノイド元素の基本的な性質を概説します。
電気抵抗や磁性を中心に話を進めますが、化学的性質や放射
性特性にも言及する予定です。次にアクチノイド化合物の超
伝導ついて内外の注目された成果を紹介します。磁性超伝導
体としてはシェブレル相が古くから知られていますが、磁性
は希土類の4f電子、超伝導はMoの4d電子が担っていることが
明らかになっています。一方、UGe2やURhGeでは磁性と超伝
導は共にウランの5f電子に由来しており、強磁場の存在によ
り超伝導が安定化したり再発現する現象はアクチノイド以外
では前例がありません。最後に我々が金属材料研究所大洗セ
ンターで行ってきたアクチノイド化合物の試料作成、測定技
術、実験結果について紹介します。
第56回講演会 2015年10月1日(木)15:10~16:40
小林 美加 氏 (東京大学生産技術研究所)
水の特異性からせまるガラス形成の起源
概 要:水は地球上で最も基本的な物質のひとつであるが、密度の4℃極大などの
特異的な性質を示すほか、結晶化しやすく、通常の冷却方法でガラスにすることは
困難である。ところが、塩などの添加によりガラス形成能は劇的に増加する。
これは、塩の添加が、水の局所安定構造とされる「5つの水分子からなる
四面体構造」を破壊することによると考えられる。
ここでは、主に塩化リチウム水溶液を例にとり、相図とガラス形成能の関係に
ついての実験的研究結果を示し、ガラス形成能やフラジリティが、局所
安定構造と結晶構造との競合関係から説明可能であることを紹介する。
以上は、純粋な水の圧力依存性や、共融混合物に特徴的なV字型の相図を
示す金属ガラスやイオン導電性ガラスのほか、実用化されているガラスにも
拡張可能である。さらに、多分散系などについても、「結晶化を阻害する要因が
ガラス形成の鍵を担う」、という共通の概念で説明できると考えている。
参考文献:
[1] H. Tanaka, J. Phys. : Condens. Matter 15, L703 (2003).
[2] M. Kobayashi and H. Tanaka, Phys. Rev. Lett. 106, 125703 (2011).
[3] M. Kobayashi and H. Tanaka, J. Phys. Chem B 115, 14077 (2011).
第55回講演会 2015年7月23日(木)15:10~16:40
山口 尚秀 氏 (物質・材料研究機構)
ダイヤモンドの表面電気伝導とその制御
概 要:ダイヤモンドは多くの優れた特性を持ち次世代の半導体材料として
期待されています。ただ、シリコンなどに比べて不純物のイオン化エネルギーが
大きいため(ボロンで0.37 eV)、電気伝導を担う電子やホールの
密度を上げようとすると、高密度に不純物をドープする必要があります。
しかしそうすると、不純物は散乱体としても働くので、移動度が下がってしまいます。
一方、ダイヤモンド表面の炭素の未結合手を水素とつなげてやると、
ボロンなどの不純物を入れなくても表面に電気伝導が現れることが
知られています。われわれはこのような水素終端ダイヤモンドの
表面電気伝導を電場によって制御し、高移動度の金属状態の形成や
量子振動の観測に成功しました。[1,2] 講演では、ダイヤモンドの電気的性質の
特徴やデバイス応用に向けた最近の研究を紹介します。
参考文献:
[1] Yamaguchi et al. J. Phys. Soc. Jpn. 82, 074718 (2013).
[2] Yamaguchi et al. Phys. Rev. B 89, 235304 (2014).
第54回講演会 2015年6月25日(木)15:10~16:40
大嶋 則和 氏 (国立研究開発法人 科学技術振興機構)
スピントロニクス
- ナノメートルスケールの磁気伝導現象と新しいデバイスの研究開発 -
概 要:電子には電荷とスピンという二つの顔があります。電荷の動きは電気伝導現象であり、
スピンは電子の軌道運動とともに物質の磁気的性質を引き起こします。磁場による
電流の変化(電流磁気効果)など両者の関係する現象は古くから知られていますが、
近年、物質の構造や性質がナノメートルスケールで制御できるようになると、
電荷とスピンの相互作用が強調された様々な面白い現象が発見されるように
なりました。このような現象を扱う研究はスピントロニクスと呼ばれ、現在基礎、応用の
両面から多くの注目を浴びています。
本講演では、スピントロニクスの典型的な現象と、それを利用した応用技術について
紹介します。上記のようにスピントロニクスは極薄膜の作製技術や微細加工技術が
進んだ結果発展してきた新しい学問ですが、既に様々なものに応用され、
製品として実用化されています。その代表例が、電気抵抗が磁化の方向に
依存して非常に大きく変化する巨大磁気抵抗効果(Giant Magnetoresistance:GMR)
です。磁化方向に依存したスピンの散乱など基礎的な物理の発展に寄与すると
同時に、ハードディスクに用いられる超高感度な磁気センサ(再生磁気ヘッド)に
応用され飛躍的な容量の増大に貢献しています。また、電流を磁性体に
通じることで磁化を反転させたり、磁壁を動かすスピントランスファートルクという現象には、
磁場を使わずに磁化方向が制御できるという特徴があります。これを生かして
新しい情報記憶素子MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)
への適用が期待され研究開発が進んでいます。講演では、このMRAMを中心として、
スピントロニクスの魅力的な現象がどのように応用されているかについてお話します。
第53回講演会 2015年5月28日(木)15:10~16:40
守 真太郎 氏 (北里大学理学部)
非線形ポリア壺の相転移と情報カスケード実験
概 要:壺の中に赤玉と青玉がひとつづつ入っているとする。壺から玉をひとつランダムに
取り出し、取り出した玉と同じ色の玉を加えて壺に戻す操作を繰り返す。
すると、最初は赤と青が同じ確率で選ばれるが、それが赤か青かの影響が
いつまでも残る。この過程をポリア壺と呼び、感染現象のもっとも単純な
モデルのひとつである。このモデルでは、次に赤玉が選ばれる確率は
壺の中の赤玉の比率zに等しいが、この確率を非線形の関数f(z)に
一般化したモデルを非線形ポリア壺と呼ぶ。この場合、赤玉の比率は
f(z)の安定不動点に収束する。
本講演では、非線形ポリア壺について、
(1) f(z)のパラメータ変化による安定不動点の個数の変化は最初の
玉の色の影響がいづれきえる相といつまでも残る相の間の
相転移であること[1]
(2) 情報カスケード実験という集団実験による実現と相転移現象の検証[2]
の2点についてお話します。
参考文献:
[1]S.Mori and M.Hisakado, J. Phys. Soc. Jpn. 84,054001-054013(2015)
[2]S.Mori, M. Hisakado and T. Takahashi, Phys.Rev.E86(2012)026109-026118.
第52回講演会 2015年4月23日(木)15:10~16:40
山田 祐理 氏 (東京電機大学理工学部理学系化学コース)
定圧分子動力学法によるLennard-Jones系の相境界
概 要:化学におけるコンピュータの利用,現在では計算化学と呼ばれている
研究分野の興りは,かのENIACが生み出されてすぐの1950年代に遡る。
以降,コンピュータの性能が飛躍的に発展していくとともに,計算化学は
その重要性を増すばかりか,理論や実験と並ぶ第三の研究手段として,
もはや化学において欠くことのできない位置を占めるようになった。
近年はスーパーコンピュータにより,数千万オーダーの粒子からなる
系を計算することも可能になってきた一方,家庭用レベルの
コンピュータで行える規模の計算モデル・計算手法も数多く提案
されており,他分野の研究者が補助的手段としてシミュレーションを
扱えるようにもなってきた。
講演者はこれまで,複雑な系をいかに単純化して(定性的にでも)
表せるかに着目して研究を進めてきた。本講演では,分子シミュレーションの
一手法である分子動力学法のあらましとともに,Lennard-Jones分子系の
相境界を簡便に得るために新たに開発した分子動力学計算の
手法について紹介する。
第51回講演会 2015年1月8日(木)15:10~16:40
辰巳 創一 氏 (京都工芸繊維大学)
細孔中に封入された単純液体の新規な相転移
概 要:
物質を結晶化させずに冷却させると過冷却液体となり,分子の乱雑な構造を保ったまま
流動性を失ってガラス状態になる。ここで、ガラス状態に至ることなしに低温側へ過冷却
液体を更に冷却したとき、ある温度T_K(カウツマン温度)で液体のエントロピーが
結晶のエントロピーよりも小さくなるというカウツマンパラッドクスがある。
このパラドックスへの説明として、T_Kに達するまでに液体状態でなんらかの転移が
存在する可能性が示唆されており、その候補として、近年水系などで見られるような
液体液体転移などが提案されており、間接的にではあるがその証拠のような物も
出てきている。しかしながら従来調べられている物質は、物質間相互作用が
水素結合に代表されるように非常に強い物質が多い。本研究では、未だに
分子間相互作用が小さく単純なシクロヘキサンを用いて、相互作用の詳細によらない
液体の性質に迫ることを試みた。シクロヘキサンのような単純な分子では,通常の
冷却方法では結晶化してしまい、過冷却液体の性質を調べるのは難しい。
そこで,本研究では分子を細孔径が数nmの細孔中に封入することで結晶化を
抑制している。試料の封入には、MCM-41、SBA-15、TMPSと呼ばれる、メソポーラス
シリカを用いており、細孔径を大体2 -7nmの間で系統的に変化させ、測定は断熱型
熱量計による精密熱容量測定と自発的エンタルピー緩和測定、KEKのBL-8Aにおける
X線粉末回折実験による構造解析実験を行った。
その結果十分小さな細孔中のシクロヘキサンが細孔径によらず154Kで新規な相転移
現象を起こすことを発見した。この転移は非常に小さい1次転移であり、転移温度が
細孔径によらないことや、バルクの転移温度の細孔径依存性の関係から、バルク中で
知られていたような結晶相への転移とは異なることが結論される。また、X線粉末回折からも
液体に特徴的な1次ピークピーク位置、強度が転移の前後で変化する様子も観察
されており、ある種の液体液体転移ではないかと考えている。本講演では、熱測定の
概要からはじめて、以上で述べたような我々が発見した新規な相転移について概説したい。
第50回講演会 2014年11月27日(木)15:10~16:40
中原 明生 氏 (日本大学理工学部)
ペーストのメモリー効果と乾燥破壊の制御
概 要:
粉と水を混ぜた高濃度ペーストは塑性ゆえに揺れや流れなどの動きを記憶し、その記憶は
その後乾燥させた時に発生する亀裂パターンの形状として視覚化される(ペーストのメモリー効果)[1]。
例えば、ペーストが揺れを記憶した時は亀裂は揺れに対し垂直に進行し、一方、ペーストが流れを記憶
した時は亀裂は流れに対し平行に進行する[2]。理論的研究によりペーストが揺れを記憶するメカニズムは
残留張力理論で説明できること[3-4]が、実験的研究によりペーストが流れを記憶できるかは水中での
粒子間の相互作用の性質で決まること[5]が示された。
近年、揺れや流れを記憶したペーストに対し
、短時間超音波を照射することでペーストの記憶を消去できることが見出された[6]。ペーストのメモリー
効果の工学的な応用例も含め、これまでの研究の流れと今後の発展について解説したい。
[1] A. Nakahara and Y. Matsuo, "Imprinting Memory Into Paste and Its Visualization as Crack Patterns in Drying Process", J. Phys. Soc. Jpn.74 (2005) 1362.
[2] A. Nakahara and Y. Matsuo, "Transition in the pattern of cracks resulting from memory effects in paste", Phys. Rev. E, 74 (2006) 045102(R).
[3] M. Otsuki, "Memory effect on the formation of drying cracks", Phys.Rev. E 72 (2005) 046115.
[4] Ooshida T., "Continuum theory of memory effect in crack patterns of drying pastes", Phys. Rev. E 77 (2008) 061501.
[5] Y. Matsuo and A. Nakahara, "Effect of interaction on the formation of memories in paste", J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 024801.
[6] 中原明生、松尾洋介、伊藤丸人、米山瞭汰、「超音波照射による固液混合材料の異方構造の消去」、特願2014-038777、2014-2-28.
第49回講演会 2014年10月30日(木)15:10~16:40
宮里 裕二 氏 (東京電機大学理工学部 理学系化学コース)
酸塩基平衡によってNラジカルを分子内に発現するルテニウムージオキソレン錯体
概 要:
アミニルラジカル(R2N・ R = alkyl, H)は、様々な有機化合物から水素原子(H・)の
引き抜き反応を誘発する反応性の高いラジカル種として古くから知られている。しかしながら、
このような反応性の高いラジカル種を生成するには、一般に強力な酸化剤の使用や光照射による
ホモリティックな結合解離反応を行う必要があった。本講演では、我々が開発したルテニウムを
金属中心にもつ金属錯体がどのようにして酸塩基平衡という温和な環境下でアミニルラジカルを
容易に発現できたのか、その発現機構とともに反応利用についても紹介する。
第48回講演会 2014年10月2日(木)15:10~16:40
沖川 侑揮 氏
((独)産業技術総合研究所 ナノチューブ応用研究センター グラフェン材料チーム)
プラズマを用いたグラフェン合成の開発
概 要:
グラフェンはハニカム構造をした炭素のみで構成された物質である。鉛筆の芯であるグラファイトは
蜂の巣状の構造が何層にも重なった構造をしており、その一枚一枚がグラフェンにあたる。グラフェンは
高移動度、高いフレキシブル性、高熱伝導性を有しており、フレキシブル透明導電膜や放熱材料などの
次世代デバイスへの応用が期待されている。一方、産業応用の観点から、グラフェンの大面積かつ
高スループット化、また更なる高品質化が求められる。これらの課題を解決するために、産総研では
プラズマ処理技術を用いたグラフェンの合成技術の開発に取り組んできた。本講演では、これまで
我々が取り組んできたグラフェン合成技術や評価技術、またグラフェンを用いたアプリケーションについて紹介する。
第47回講演会 2014年7月24日(木 15:10~16:40
向山 義治 氏 (東京電機大学理工学部理学系化学コース)
電気化学振動現象 -水の電気分解による水素発生反応の可能性
概 要:
水の電気分解(Water electrolysis)は、150年以上も前に発見されており、
最もよく知られた電気化学反応です。陰極上で水(もしくは水素イオン)が還
元されて水素が発生し、陽極上では水(もしくは水酸化物イオン)が酸化され
て酸素が発生します。水の電気分解は、クリーンなエネルギーといわれる水素
を水から製造できることから、近年大きな注目を集めています。また、水素発
生反応(Hydrogen evolution reaction)および酸素発生反応は基本的な電気化
学反応であることからも、今日までに膨大な研究がなされております。タイト
ルに Hydrogen evolution reaction または Water electrolysisを含む学術論
文は少なくとも1130報以上もあります。
講演者は、このような古い反応である水の電気分解において,電気分解の電
圧(陰極と陽極の電極電位の差)が自発的に振動することを発見しました。振
動は電極として用いる金属の種類によらず発生します。また、電圧が 0.8 Vも
振動するというダイナミックな現象であることから、講演者よりも前に発見さ
れていても不思議ではありません。講演では、なぜ振動の発見に至ったのかの
エピソードも交え、電圧が自発的に振動するメカニズムについて紹介します。
近年、水の電気分解によって溶解度以上の水素を溶液中に分散させることがで
きるようになっています。水素を含む水は医療や産業へ応用されつつあり、水
の電気分解による水素発生反応の可能性についても講演で紹介します。
第46回講演会 2014年6月26日(木 15:10~16:40
広沢 哲 氏 (独立行政法人物質・材料研究機構)
永久磁石のはなし -- 磁石が地球を救う理由(わけ)と物質が磁石になるわけ
概 要:
永久磁石の研究開発が最近になって再度、盛んになっています。
その理由は、ハイブリッド自動車や電気自動車、エアコンのコンプレッサーなどに
超高性能の永久磁石が大量に使われるようになった結果、一部の原料資源が
心配になるほど生産量が増え続けていることにあります。
さらに今後は風力発電などにも永久磁石が大量に必要になる可能性もあると
言われています。永久磁石がこれらのエネルギー変換機器や設備に必要なのは、
変換効率が高くなるからで、そこで節約できるエネルギーを世界規模で積算すれば
発電所何基分にも相当する膨大な量になります。
講演者が代表を務めている
元素戦略磁性材料研究拠点は、原料資源を心配せずに大量に製造できる高性能永久磁石を作り出すには
どうすべきかを研究しています。そもそも物質が永久磁石になるということは
どういうことなのか、そのためにはどういった性質が物質に必要なのか、
どのようにして新しい材料を作り出そうとしているのか、可能性はあるのか、など、
基本的で重要なことについて、できるだけ直感的にお話します。
第45回講演会 2014年5月29日(木) 15:10~16:40
高安 美佐子 氏 (東京工業大学)
経済物理学 -- ビッグデータから人間社会のどんな動きが見えるか
概 要:
21世紀、インターネットや携帯電話がインフラとして整備され、またコ
ンピュータの計算能力が劇的に進歩しています。そのような現代、ビッグ
データを通して個々の人間の活動と社会や経済の現象との関連性を理解す
る研究が盛んに行なわれています。
例えば、日々のニュースで必ず目にする為替市場のドル円レートは、
決して安定することなく常にゆらいでいます。市場価格の上がり下がりは
確率的なものとする研究は100年以上の歴史がありますが、近年入手でき
るようになった詳細な金融市場のデータは、1ミリ秒の時間分解能、市場
参加者個々の注文などを含み、20年前と比べて100万倍くらい情報量を
含むようになっています。そのようなデータを分析すると、市場価格のラ
ンダムな変動は、液体中のコロイド粒子の運動と類似の現象として、コロ
イド粒子と水分子の相互作用に相当する量が定量的に観測できるようにな
ってきました。同様に、企業に関するビッグデータを分析することで、
経済活動の中で、企業同士がどのような相互作用をし、その結果、どのよ
うにお金が流れていくのか、という問題に対しても、物理学の視点に基づ
いた方程式をたてることができます。その式をコンピュータで解くことに
より、様々な状況下での経済予測のシミュレーションを行なうことができ
るようになり、その成果は既に実務に活用されています。
経済物理学が取り組んでいるのが、個におけるミクロの性質を用いて、
集団としてのマクロな現象を説明する統計物理学をもちいて社会の現象を
理解することです。
第44回講演会 2014年4月24日(木) 15:10~16:40
小西 輝昭氏 ((独)放射線医学総合研究所)
マイクロビーム細胞照射装置の開発とその低線量放射線影響研究への応用
概 要:
放射線影響研究(放射線生物学)の分野において、放射線に
対する単一細胞レベルでの応答メカニズムに関する研究が盛んに
進められている。その中でも、マイクロビーム細胞照射装置は、
放射線を直径マイクロメートルにまで集束して哺乳類培養細胞へ
“狙い撃ち”を実現する放射線発生装置である。
このような装置の特殊性から、照射された細胞の近傍の照射されて
いない細胞にも放射線の影響が表れるという放射線誘発バイスタン
ダー細胞応答に関する研究に活用されている。世界トップレベルの
性能を有する陽子線マイクロビーム細胞照射装置(Single Particle
Irradiation System to Cell; SPICE)の開発と現状、本装置を
用いた低線量放射線影響研究について紹介する。
第43回講演会 2014年1月9日(木) 15:10~16:40
平野 太一氏 (東京大学生産技術研究所)
粘性測定に挑む
概 要:
「ねばねば・さらさら」と聞けば多少なりともイメージが
湧く一方、「粘性」と言われてもぴんと来ない、という方々は
多いのではないか?
液体や気体などの流れを左右する物性値の代表例である粘性の
物理的な意味や産業応用上の重要性を解説するとともに、
粘性を測るための様々な技術・手法や、意外と知られていない
粘性と日常生活の密接な関わりについても紹介する。
日 時:
場 所: 東京電機大学理工学部 理学系会議室(1407室)
第42回講演会 2013年11月28日(木) 15:10~16:40
大村 英樹 氏 ((独)産業技術総合研究所)
位相制御レーザーパルスによる分子トンネルイオン化の量子制御
概 要:
レーザー光のコヒーレントな性質を利用して物質の量子状態や
量子ダイナミクスを直接操作し、物性・機能を量子制御(コヒ
ーレント制御)する研究が近年盛んである。講演者等は波長の
異なるレーザーパルスの相対位相差を精密に制御し、気体分子
の異方性光トンネルイオン化に成功するとともに、その帰結で
ある分子配向操作(配向選択分子イオン化)を世界に先駆けて
実現した。このような気体分子の配向操作により、分光計測の
際に生じる分子ランダム配向に起因する情報平均化が回避され、
情報量が飛躍的に増大する。幾つかの実験結果を通して、分子
操作技術としての重要性や将来性が述べられる。
第41回講演会 2013年11月7日(木) 15:10~16:40
石井 聡 氏 (東京電機大学理工学部)
カーボンナノチューブとナノデバイス
概 要:
カーボンナノチューブ(CNT)は、炭素のみから構成される直径が
ナノメートルオーダーの非常に細い筒状物質である。その質量は
アルミニウムの約半分と軽いものの、機械的強度は鋼鉄の約20倍
も高く、熱伝導率も銅の10倍以上もある。特に電気特性は特徴的で、
電流密度は銅の1000倍、電子移動度はSiの10倍もあり、金属にも半
導体にもなる。こうしたCNT特有の物性は結晶構造に依存しており、
基礎だけでなく多様な特徴を組み合わせた技術応用も積極的に研究
されている。本フォーラムでは、CNTの合成と構造制御をはじめとし
て、電気特性やCNTを利用したナノデバイスの開発について紹介する。
第40回講演会 2013年9月26日(木) 15:10~16:40
田中 慶太 氏 (東京電機大学理工学部)
脳磁図と脳機能計測
概 要:
脳磁図は、脳機能の非侵襲的計測法のひとつで、頭部を覆
う数百点の超伝導磁束量子干渉計(SQUID)により計測される。
この特徴として、脳磁図は脳波に比べ介在組織(頭皮や頭蓋
骨など)の影響を受けにくいため、センサの感度は近傍の神
経活動に対して選択的に高くなる。よって,特に大脳皮質に
活動源がある場合の精密な測定に適していると考えられてい
る。
本フォーラムでは、脳磁図が捉えている脳内神経活動の機
序や、我々が取り組んでいる脳磁図を用いた視覚,聴覚,体
性感覚の高次脳機能評価の基礎的研究内容を紹介する。
第39回講演会 2013年7月31日(水) 15:10~16:40 大久保 毅 氏 (東京大学物性研究所)
フラストレート磁性体におけるトポロジカル励起の秩序化
概 要:
フラストレーションとは、複数の最適化条件が競合した結果、
系がそれらを同時に満たすことが出来ない状態であり、「あ
ちらを立てれば、こちらが立たず」という状況になっている。
本講演では、このようなフラストレーションの典型的な舞台
である、二次元三角格子上の古典ハイゼンベルグ反強磁性体
の秩序化について、モンテカルロシミュレーションと平均場
近似を用いて解析した結果を紹介する[1]。
三角格子ハイゼンベルグ反強磁性体の基底状態は、相互作用
が再近接のみの場合には、120度構造と呼ばれる格子に整合な
状態である。一方、二次近接・三次近接相互作用が主体とな
る場合には格子に非整合なスパイ ラル構造が基底状態になり、
その場合、格子の三回回転対称性を反映して、スパイラルを
特徴付ける波数の方向に関して基底状態が三重に縮退する。
我々は、格子に非整合なスパイラル状態が現れる場合に、磁
場中では、複数の波数秩序が共存する多重Q秩序状態が有限温
度で安定化されることを明らかにした[1]。特に、中程度の磁
場で実現している、トポロジカル励起である“スカーミオン”
が、三角格子を形成した“スカーミオン格子”と呼ばれる興味
深い状態を紹介しつつ、フラストレート磁性体の秩序化につい
て議論したい。
[1] T. Okubo, S. Chung and H. Kawamura, Phys. Rev. Lett.108,017206 (2012).
第38回講演会 2013年6月27日(木) 15:10~16:40
古府 麻衣子 氏 (東京大学物性研究所)
中性子散乱で見たイオン液体の階層的運動
概 要:
「イオン液体」とは室温で液体状態をとる塩の総称である。
イオン液体は熱力学安定性と優れた電気化学特性を持ち、新
規な多機能物質として注目されている。イオン液体は食塩の
ように陽イオンと陰イオンからなる塩であるが、その融点は
著しく低い。その理由のひとつは、かさ高い陽イオンがクー
ロン相互作用を弱めていることである。イオン液体の一番の
特徴はその階層的な構造である。陽イオンのアルキル鎖から
なる非極性ドメインと陽イオンの極性部分および陰イオンか
らなる極性ドメインが存在することが示唆されている。
我々は、階層的な構造に対応した運動があると考え、中性子
散乱手法を用いてイオン液体のダイナミクスを調べた。
測定の結果、アルキル鎖の局所運動、陽イオンの拡散運動
(イオン拡散)、ドメインの運動をそれぞれ観測することに成
功した。イオン液体の階層的運動の全貌を捉えたのは我々が
初めてである。講演では、中性子散乱の原理や特長について
もわかりやすく説明したい。
第37回講演会 2013年5月30日(木) 16:00~17:00
藤江 遼 氏 (東大生研FIRST合原プロジェクト)
多数派選好/少数派忌避の行動原理による合意形成
概 要:
各個人の選択がどのような条件で揃うのか,もしくは,併存するの
かというコンセンサス問題は,合意形成,言語淘汰,寡占市場など
多くの社会現象に関係し,その結果は人の選択行動に強く依存する.
本講演では,コンセンサス問題の例として言語間競争のモデル [1]
を用い,多種共存の安定性について議論する.2言語系では区別で
きない「多数派選好」と「少数派忌避」という行動原理をN言語系
に導入し,それぞれの行動原理における共存解の安定性条件を求め
た.その結果,少数派忌避の行動原理のもとでは,言語数の増加に
伴い,多種共存のパラメータ領域が増大することを示した[2].
[1] D.M. Abrams and S.H. Strogatz, Nature 424, 900 (2003)
[2] R.Fujie, K.Aihara and N.Masuda, J.Stat.Phys.151,289(2013)
第36回講演会 2013年4月25日(木) 15:10~16:40
山室 憲子 氏 (東京電機大学理工学部)
中性子準弾性散乱によるリシンベタイン水溶液のミクロダイナミクス
概 要:
動植物のある種のものは,環境ストレスを受けたとき,体内に生体
保護物質を合成・蓄積して対処する。ネムリユスリカの場合,極端
乾燥条件下ではトレハロース(糖類の1種)が生体保護物質として
働き,個体がガラス状態になることで蘇生を可能にしていることが
知られている。
グリシンベタイン(GB)は, 分子内にカチオンとアニオンの両
方を持つ両性イオンで、稲などの植物の生体保護物質として知られ
ている。水溶液の物性はトレハロースとは大きく異なり,潮解性が
強い,水溶液の粘度・密度上昇が小さいなどの特徴をもち,生体保
護のメカニズムはトレハロースと大きく異なると考えられる。GBは
どのように水と相互作用しているのか? 水の拡散運動はGBにより
どのように変化するのか? のGB水溶液のミクロダイナミクスを明
らかにする目的で,中性子準弾性散乱法をおこなった。最終的には
GBの生体保護のメカニズムを明らかにすることを目指している。
講演では、中性子準弾性散乱の基本から解説する。
特別講演会 2013年4月19日(金) 15:10~16:40
本庄 春雄氏 (九州大学総合理工学研究院)
日本におけるこの半世紀の内閣支持率の統計的性質
概 要:
1960年6月の岸内閣から2013年1月の第2次安倍内閣までのほぼ半世
紀にわたる内閣の毎月の支持率の統計的性質を調べた。支持率の
時間的変化は同一内閣で支持率が比較的、小幅に増減する場合と
内閣が交替する場合で支持率が比較的、大幅に上昇する場合の2
種類に分類され、いずれも対数正規分布になっている。総じて、
支持率は時間と共に下がっていき、内閣改造を実施して支持率向
上を図るがその効果は短期的である。内閣支持率のダイナミクス
は、現状維持力と交替力の拮抗で決まっていることがデータから
分析され、そのクリティカルな値はおおよそ20%となっている。
また、内閣交替時における支持率のゆらぎは支持率が小さいほど
大きいため、内閣が替わったからといって支持率が大きくなると
は限らない。以上、解析は現在も進行中であるため途中経過では
あるが報告を行う。
第35回講演会 2013年1月10日(木) 15:10~16:40
吉留 崇 氏 (横浜市立大学)
水のエントロピー効果に主眼を置いたF1-ATPaseの回転機構
概要:
F1-ATPase は、ATP の結合→加水分解→分解生成物の放出と
いうサイクルの間に、まるでモーターのように回転するタン
パク質複合体である。回転のメカニズムの解明は生命現象を
理解する上で重要であり、これまで主に1分子測定を用いて研
究が行われてきた。
一方、回転メカニズムの微視的な観点からの理解は進んでい
なかった。F1-ATPaseはいくつかのサブユニットから構成され
るタンパク質複合体であるが、構成するサブユニット間の充
填状態が著しく非対称であることが知られている。我々はこの
充填状態の非対称性に着目し、水のエントロピー効果の観点か
ら解析を行った [1]。その結果を元に、「水のエントロピー効
果によって生じた充填状態の非対称性が、上記のサイクルの過
程で回転を誘発する」という描像を提案した [1]。さらに最近、
提案した描像の妥当性を部分的に示すことに成功した[2]。
[1] T. Yoshidome, Y. Ito, M. Ikeguchi, and M. Kinoshita,
J. Am. Chem.Soc. 133, 4030 (2011).
[2] T. Yoshidome, Y. Ito, N. Matubayasi, M. Ikeguchi,
and M. Kinoshita, J. Chem. Phys., 137, 035102 (2012).
第34回講演会 2012年11月29日(木) 15:10~16:40
佐野 幸恵氏 (日本大学理工学部)
ソーシャルメディアデータを用いた人間行動の定量化
概要:
ブログやツイッターに代表されるソーシャルメディアの普及により,
ウェブにおける人間の行動を,大規模に定量化して観測することが
可能となった.個人が自由な意志を持つ,人間の行動に統計的な法
則などあるのか.もしあるとすると,どうやって観測するのか.
本講演では,主にブログのデータを用いた研究成果を紹介する[1].
日常的な語の出現頻度で観測した揺らぎのスケーリング則,個人の
投稿行動のバースト性など興味深いトピックがある.データの解析
手法や,それに伴う問題点など基本的な部分から導入し,実社会と
ソーシャルメディアの関わりについても紹介する.また2011年東日
本大震災時,ツイッター内で起こったデマの拡散についても触れる.
[1]「ソーシャルメディアの経済物理学」(高安美佐子編著,日本評論社)
第33回講演会 2012年10月25日(木) 15:10~16:40
間宮 広明 氏 (独立行政法人 物質・材料研究機構)
三角関係からナノ集積制御まで ~磁石の集団が示す多様な振舞い~
概要:
物質を分割し、その根源的な要素の本質を明らかとすることは
物理学の大きな目標であるが、要素の本質がわかっただけでは全
体の振舞を予測できない。例えば、棒磁石にもう一つの棒磁石を
NSの軸方向から近づければ同じ向きに付き、軸の横方向から近づ
ければ逆向きに付くが、そこに3つめの磁石を横から近づければ、
どうなるか。上から見て軸が正三角形の位置になるようにおけば、
NSがどちらを向いてもエネルギーの損得は変わらない。あちらを
立てればこちらが立たず、という三角関係のフラストレーション
がその振舞を複雑にしている。このように日頃慣れ親しんだ棒磁
石でさえ、その並び方ひとつでその振舞が大きく変わる。
講演では、まず、結晶の中に配列した微小な磁石であるスピン
の集団の多様な振舞をスピングラスを中心に紹介する。ただし、
あちらにもこちらにも遠慮するような秩序は、多くの場合、極低
温でしか安定でいられない。そこで、最近、数千から数十万個の
スピンが集まってできたより大きなサイズの磁石を、ナノテクノ
ロジーを活かして思い通りに並べ、室温でそうした振舞を再現し
ようとする試みが進められている。講演の後半では、こうした試
みの一部を紹介し、最後に、その応用への展望を議論したい。
第32回講演会 2012年9月27日(木) 15:10~16:40
大槻 道夫 氏 (青山学院大学理工学部)
摩擦の素過程~摩擦界面の局所滑りとアモントン則の破れ~
概要:
滑り摩擦に関しては古来より様々な研究があるが、多くの基本的問題が未解決で
のまま残されている。例えば、滑り摩擦の基本法則として、摩擦力が物体加えられ
た垂直荷重に比例するというアモントン則が知られているが、この法則の成立機構
や条件については、未だに確固たる理解がなされていない。近年、これらの研究に
おいて大きな進展がある。その1つは、摩擦のきっかけとなる摩擦界面での局所滑り
の発生とその伝搬、そしてそれがマクロな運動につながる過程を実験的に見ること
ができるようになったことである。
このような滑り摩擦の素過程を理論的に理解するために、我々は弾性体の解析計
算を行い、そうした局所滑りの挙動が、ある種の安定性解析から理解できることを
発見した[1]。さらに、局所的な滑りの大きさによってマクロな摩擦力がスケールさ
れることも発見した。このことから、摩擦の基本法則として知られているアモント
ン則が、ある条件で系統的に破れることが予言される。この予言の成立は最近の実
験で確認されている。講演では、こうした実験との対応についても詳細に議論したい。
[1]. M. Otsuki and H. Matsukawa, arXiv:1202.1706
第31回講演会 2012年7月26日(木) 15:10~16:40
望月 敦史 氏 (理化学研究所/東京工業大学)
生命の複雑な制御ネットワークを数理的に解く
概要:
生命システムの解明が進んだ結果、生物の高次機能には様々な
遺伝子や蛋白質などの生体分子がかかわっていることが、分かっ
てきた。多数種の生体分子が制御の複雑なネットワークを作り、
その複雑なシステムの全体から生体分子のダイナミクスがつくら
れ、そのダイナミクスこそが生命機能の本質なのだと考えられて
いる。しかし、制御ネットワークの構造が、分子の活性ダイナミ
クスに対して、どの様な影響を与えるのか、或いはどの様な意味
を持っているのか、といった理解はほとんど進んでいない。これ
に対して私は、ネットワークの構造とダイナミクスとの関係を明
確に示す強力な理論を構築した。ホヤの発生における遺伝子ネッ
トワークや、シグナル伝達系における生体分子反応など、複数の
ネットワークを具体的に取り上げながら、この理論を紹介する。
第30回講演会 2012年7月5日(木) 15:10~16:30
好村 滋行 氏 (首都大学東京)
生体膜における不均一構造の物理
概要:
生体膜は様々な脂質やステロール、タンパク質、糖などで構成
されており、細胞の機能にとって不可欠な役割を果たしている。
様々な生物学的な実験の蓄積により、これらの構成成分は均一
に分布しているのではなく、動的なドメイン(ラフト)を形成し
ていることが明らかになってきた。このような生体膜の新しい描像
に触発されて、人工的な脂質二重膜を用いた物理化学的な研究が、
2000年以降に世界中で大きく進展した。脂質膜におけるドメイン
形成は相分離現象として理解することが可能である。
講演では生体膜の相挙動、構造、ダイナミクスに関して、
ソフトマター物理学の観点から解説を行いたい。
特に生体膜のダイナミクスにおける流体力学的相互作用の
重要性について議論する。
第29回講演会 2012年5月31日(木) 15:10~16:30
鈴木 徹 氏 (東京海洋大学)
食品の物性とガラス状態、ガラス転移の応用
概要:
物性物理学の研究対象であるガラス転移現象、ガラス状態
は我々の身近な食品の世界にも頻繁にみられる。むしろ我々
人間はそれを利用して生きてきたといっても過言ではない。
本講演では、食品の加工や保存性とガラス転移との関係に
ついて概説するとともに、トピックとして日本の伝統的な食
材であるカツオ節のガラス転移の挙動と応用、天ぷら衣など
フライ食品とガラス転移の関係、さらに澱粉のガラス状態の
変化(エイジング)と吸湿性の変化などについて説明したい。
第28回講演会 2012年4月26日(木) 15:10~16:30
高 橋 栄 一 氏 (産総研)
身近な放電プラズマ ~わからないこと、超高速計測から見えてきたもの~
概要:
プラズマは実は身近なものです。自然界では雷や太陽もプラズマですし、
生活の中では、蛍光灯、空気清浄機、車のスパークプラグなど様々なもの
用いられています。その中でも非常に昔から研究されてきた「放電現象」
に、最新の超高速計測を適用して見えてきたものを紹介します。放電現象
は良くわかっているはずなのに、実は良く分かっていないこと、その形に
関しての物理的な側面や、どんな可能性があるのかを述べます。
第27回講演会 2011年12月15日(木) 15:10~16:30
松下 貢 氏 (中央大学理工学部)
バクテリア・コロニーの形成-実験とモデル化-
概要:
生き物の集団的な振る舞いを問題にするとき、その集団を
構成する個体の主な特徴は増殖と運動であろう。これはい
ろいろな生物の集りから人間による村落や都市形成に到る
まで、共通しているように思われる。
ここでは容易に実験できる例として細菌を取り上げ、この
二つの特徴が織りなす多彩なコロニー・パターンの形成を
議論してみる。また、バクテリア・コロニー形成のモデル
が反応拡散方程式を基礎にこれまでにいくつか提案され、
計算機シミュレーションがなされている。
それらを紹介し、実験の立場から現在どこが問題かを批判
的に議論してみたい。
第26回講演会 2011年11月24日(木) 15:10~16:30
酒井 啓司 氏 (東京大学生産技術研究所)
さざ波を数えてもどうにもキリがない
概要:
光、音、水面のさざ波など波は身近にあふれています。
一方で波の物理はちょっとややこしい印象があります。
例えば意地悪な物理の先生は、「光は波 である」と教
えたり、「やっぱり光は粒である」といってみたり、波
を使って学生を混乱させることを楽しんでいます。一体
どっちが本当でしょうか?
講演ではこのような物理の先生に対抗して、身近な波
の現象について復習します。また波を周波数ごとに分け
る技術である「分光」について、さらに 「波を数える」
実験についてお話します。とはいえ光や音に関する物理
の研究についてはみなさんもよくご存じでしょう。(ご
存じでなくてもかまいません。)では「さざ波」の研究
は?講演の最後では「さざ波を数える」ことによって液
体表面の分子の様子を観察する方法についても紹介しま
す。でも こんなことをしていったい何の役に立つので
しょうか?まあ気楽に聞いてみてください。
第25回講演会 2011年10月27日(木)15:10~16:30
西岡 昭博 氏 (山形大学大学院理工学研究科)
プラスチック成形加工技術を応用した米粉100%パンの開発

概要:
一般にパンは小麦粉から作られ、米粉では絶対に製パ
ンは不可能とされてきました。小麦粉も米粉も主成分は
同じ澱粉です。
この点では大きな違いはありませんが、両者の製パン
性(加工性)は全く異なります。これは、小麦に含まれ
るグルテンに起因します。グルテンはパン生地を捏ねる
ことで著しい粘弾性を発現するタンパクです。
米粉にはグルテンが含まれていないため、製パン出来
ないと考えられてきたのです。これが食品科学やパン職
人の常識でした。一方で、プラスチック成形加工は、
「流す」―「形にする」―「固める」が基本です。特に
成形時の樹脂のレオロジー(溶融粘度など)が大きく成
形性に影響することが知られています。我々は、プラス
チック成形加工の考え方を米粉パンの製パンに応用する
ことで、初めて従来不可能とされてきた米粉100%に
よる製パンに成功しました。
本講演ではどのような考え方で不可能を可能にしたの
かについて、学部生に理解しやすいよう平易に解説した
いと思います。
第24回講演会 2011年9月29日(木)15:10~
巾崎 潤子氏 (東京工業大学)
イオン液体、ガラス系の分子動力学
概要:
分子動力学法(MD)は、原子、分子の構造やダイナミクスを種々のタイムスケール、
レングススケールで調べられる有用な手法で、ガラス転移点近傍の遅いダイナミクスの
研究にも威力を発揮します。この講演では、
代表的なイオン液体である1-ethyl-3-methyl imidazolium nitrateのMDシミュレーション
による研究について述べます。
イオン液体とは、高融点のNaClなどとは異なり、室温付近でも液体である塩の事で、
不揮発性の環境に優しい良溶媒であることなどから、種々の応用分野で利用されています。
基礎科学の面からは、イオン伝導性ガラスの研究とガラス転移の研究を繋ぐ「要」となる系
として注目されます。イオン液体では、ガラス転移点付近の原子、分子の挙動と同様の遅い
ダイナミクスが見られ、長時間にわたる動的不均一性(遅い運動と速い運動の共存)を示す
ことが分かってきました。この動的不均一性を特徴づけるLevy分布やマルチフラクタル性に
ついて明らかにし、ガラス転移の機構やガラス構造の形成過程について議論します。
また、イオン伝導性ガラスやソフトコアなどのモデル系におけるダイナミクスとの共通点、
相違点について明らかにします。
第23回講演会 2011年7月28日(木)15:10~
鈴木芳治 氏 (物質・材料研究機構)
水のポリアモルフィズム ~水の多形~
概要:
昔から水は我々の生活に欠くことのできない物質の 1つです。
しかし、水は通常の物質とは全く異なった性質を示し、その
本質は驚くほど理解されていません。最近の水の研究で、低
温の水には2つの液体状態が存在することがわかってきまし
た。この「水のポリアモルフィズム」という考え方は、水の
液-液相転移という新しい臨界現象と関係し、今まで説明で
きなかった水の奇妙な振る舞いを解決する可能性を秘めてい
ます。本講演では、水のポリアモルフィズムの概要とこの考
え方が成立するまでの背景を代表的な実験結果を紹介しなが
らお話しします。
第22回講演会 2011年6月30日(木)15:10~
村勢 則郎教授 (東京電機大学理工学部)
クリプトビオシスとガラス転移

概要:
生物の中には環境ストレスを受けるとクリプトビオシス
(無代謝休眠状態)に陥るものがおり、ストレスが除去され
ると代謝活動は回復する。
脱水によってクリプトビオシスになるものをアンヒドロビ
オシスと呼び、線虫、輪虫、クマムシ、ネムリユスリカの幼
虫などが知られている。植物の種子、胞子もそうである。
クリプトビオシスはガラス状態であると考えられ、実際に
DSC測定によりガラス転移が観測されている生物もいる。
どのようにガラス状態に移行し、ガラス化にはどのような物
質が関与しているかは生物学的にも、また生物や食品の保存
への応用の点からも興味深い。
本講演では、クリプトビオシス研究の現状を紹介し、ネム
リユスリカやクマムシのアンヒドロビオシスの例を、実際に
または映像でお見せし、併せて線虫の凍結保存について解説
する。
第21回講演会 2011年5月26日(木)15:10~
山室 修氏 (東京大学物性研究所)
単純分子でガラス転移の謎に迫る

概要:
「ガラス」は一般的な物質の3態「気体」、「液体」、「固体」に続く
「第4の状態」であるが、その物性は未だ謎に包まれている。最も不思
議なのは、その形成過程「ガラス転移」である。液体を冷やすと大きな
構造変化を伴わず有限の温度で固化するため、“動的転移”と呼ばれる
ことが多いが、これまでの多くの研究にもかかわらず、その機構は未だ
明らかにされていない。未解明現象を研究するには、できるだけ単純な
系を選ぶのが常套手段であるが、単純な分子を普通に冷却すると、ガラ
ス転移の前に結晶化してしまう。講演者らは、気体分子を10K以下に冷
えた基板に蒸着することにより、CCl4, CS2, H2O などの剛体分子やプ
ロパン (C3H8)、プロペン (C2H4=CH2)などの極めて単純な有機分子の
ガラスの作成に成功した。それらの熱容量や中性子散乱の測定から、分
子の単純さを反映した明瞭なガラス転移を見いだしている。これらのデ
ータに関して、構造不均一性や協同再配置領域に 基づく議論を行い、
ガラス転移の謎に迫りたい。
第20回講演会 2011年4月28日(木)15:10~
丑田 公規氏 (北里大学理学部化学科)
クラゲから抽出したムチンとその周辺 -細胞外物質の化学物理-

概要:
下等動物から高等動物まで、コラーゲン、ヒアルロン酸
などに代表される細胞外物質が身体の約半分の体積を占
めている。一般にこれらは複雑な高分子であり、不均一
な空間を作ったり、潤滑や界面活性作用、バイオミネラ
リーゼションなど、様々な興味ある性質で生命を支えて
いる。クラゲの身体は、高等動物の細胞外マトリックス
の起源と言ってよく、その研究の途上、我々はエチゼン
クラゲなどから新しいムチンを発見した。このムチンの
構造解析や性質を中心に生命を支える物質の新しい見方
につてお話ししたい。
第19回講演会 2月21日(月)15:10~
金子 昌信 氏 (九州大学大学院数理学研究院)
数学最古の難問,最大の難問
数学には未だに解かれていない問題が数多くありますが,その中でギリシャ以来2000年にわたって未解決である,完全数に関する問題ついてお話しし,そこからの連想で素数や,それにまつわる現代数学最大の難問リーマン予想などについて,雑談風にお話ししたいと思います. 予備知識は何もいりません.
第18回講演会 1月13日(木)15:10~
山田 洋一 氏 (筑波大学大学院数理物質科学研究科物質創成先端科学専攻)
固体表面上で有機分子の自己組織化現象
走査トンネル顕微鏡をはじめとする表面科学の手法により、固体表面上での有機分子の自己組織化現象に関する分子レベルの基礎的研究が発展しています。自己組織化現象は、自然界の最も基礎的な現象の一つであり、生物方面だけでなく、工学、特に有機ナノテクノロジーにとっても重要です。特に有機分子-固体界面では、分子と表面原子の両者の構造的及び電子的な自己組織化が生じ、有機デバイスの特性を大きく決定付けます。このセミナーでは、表面科学やそれを支える超高真空技術を簡単に紹介し、これを用いた有機単分子層の自己組織化現象の計測手法や研究例の一部を述べたいと思います。
第17回講演会 12月9日(木)15:10~
青柳 裕子 氏 (産業技術総合研究所 ナノシステム研究部門)
硬いものと柔らかいもの創りだす物質の強靭性について
硬い物質と柔らかい物質が組み合わされた複合物質の強靭性について、破壊力学の視点からお話します。自然界には長い年月の進化を経て生み出された、軽くて丈夫な物質がたくさん存在します。それらは硬いものと柔らかいものが組み合わされていることが多く、例えば歯や骨などがその典型です。今回は、亀裂の弾性論を簡単におさらいした後、自然界に存在する硬・柔を組み合わせた丈夫な物質として、真珠層とクモの巣の丈夫さについてシンプルな計算モデルを使って明らかにしていきます。さらに、人工的な硬・柔の複合体である繊維強化プラスチック(FRP)についても紹介します。
第16回講演会 11月11日(木)15:10~
水口朋子 氏 (九州大学大学院 理学府 物理学専攻)
1成分単純液体のガラス化
ガラスとは、液体状態の不規則な配置を保ったまま固化した状態であり、液体を急速に冷却することによって実現される。ガラス化過程では、比熱の急激な変化などの熱力学的異常と、構造緩和時間の異常な増大などの動的性質が観測されている。
ガラス転移の研究において、粒子の微視的な運動を観測できる分子動力学シミュレーションは大きな役割を果たしてきた。これまで、1成分系のガラス形成シミュレーションは、結晶化を阻害するのが困難であるという理由から、ほとんど試みられていない。しかしながら、1成分系では本質的にガラス形成が不可能であるという明確な証拠はない。
本講演では、分子動力学シミュレーションを用いた、2次元系における1成分単純液体のガラス化の研究結果について報告する。
第15回講演会 10月26日(火)15:10~
工藤 和恵 氏 (お茶の水女子大学 お茶大アカデミック・プロダクション)
パターン形成:磁区パターンのシミュレーション
パターンは、自然界や日常生活の様々なところに現れます。
たとえば、空に等間隔に浮かぶ筋雲や熱い味噌汁にでてくる模様などの対流パ
ターン、化学反応によるパターン、あるいは、魚や動物の体に現れる模様などが
あります。今回は、特に強磁性薄膜に現れる磁区パターンに関して、理論とシ
ミュレーションによる研究を中心に紹介します。
第14回講演会 9月30日(木)15:10~
日高章理 氏 (東京電機大学 理工学部 理学系)
パターン認識を用いた物体検出と対象追跡
近年のコンピュータやカメラ機材の性能向上・価格低下に伴い,世界中で膨大な量の映像メディアが撮影・蓄積されて続けており,それらの映像データを自動的に分類,理解,認識する“画像認識”技術へのニーズは増す一方である.画像認識の中でも特に重要な基礎技術として,静止画や動画中から人間や自動車などの特定対象を見つけ出し,その位置・大きさ・個数などの情報を自動的に捕捉するための“物体検出”および“対象追跡”の手法がある.本セミナーでは物体検出の代表的な手法であるP.
Violaらの検出器の仕組みを紹介し,さらにその手法をより高速化・高精度化したり,対象追跡問題に適用するといった発展的研究について述べる.
第13回講演会 7月27日(火)13:30~
隅山兼治 氏 (名古屋工業大学プロジェクト研究所)
不規則性とサイズを考慮した物性物理学 -金属磁性からナノ粒子物性へ-
磁石をはじめ機能材料に多く含まれている遷移金属に関係した物性物理学の研究例についてお話します。ご存知のように、遷移金属原子の不完全電子殻を形成するd電子は、材料の特性を支配するばかりでなく、結合にも寄与しています。先ず、インバー合金の磁気的揺らぎ、低熱膨張係数の起源に関する研究を通して、純鉄が強磁性、良質のステンレス鋼が常磁性を示すことの理由を考えてみます。また、物質サイズが小さくなるにともない、量子力学的効果や表面効果が顕著になると予想されます。ここでは、遷移金属合金クラスター(ナノ粒子)に注目し、作製方法、サイズ制御、集合機構について概観するとともに、サイズが揃ったクラスターを集合させたときに、低温でトンネル型の電気伝導や磁気緩和、電子局在性が顕著になる実例について述べます。時間が許せば、2種類のクラスターの衝突過程を制御したときに生じるコアシェルクラスターについて紹介します。
第12回講演会 7月1日(木)15:10~
今福健太郎 氏 (独)産業技術総合研究所)
情報とは何か、物理の視点から
「情報」とはなんでしょう。この簡単そうで途方もない問題への、物理からの挑戦についてお話します。情報理論は「情報の記述」あるいは「情報の伝達や取得の際の数理的限界」について考察するための体系です。また量子論をはじめとする現代物理は、「物理系の記述」あるいは「物理系の振舞いや測定の物理的限界」を考察するための体系として考えることができます。あらゆる情報が物理系によって伝播すること、さらには、すべての情報の取得が測定を通じて行われることの二点を考えると、情報理論と物理の結びつきは極めて自然であることが理解できるでしょう。しかしその一方において、例えば量子論で記述され るミクロな系の不思議な振る舞いにより、両理論の融合には、単なる結びつきだけで終わらない不思議さや面白さが存在していることも知られています。量子暗号など最近の話題に触れながら、「情報」を物理として理解する面白さ(と悩ましさ)についてご紹介したいと思います。
第11回講演会 6月 7日(月)15:10~
岩田 修一 氏 (名古屋工業大学 工学部)
粘弾性流体の異常流動とその解析
粘性と弾性を兼ね備える粘弾性流体は、高分子水溶液や溶融プラスチック樹脂など身の回りにいろいろと見られます。このような流体は、常識とは異なる様々な現象や流れを示すことが知られています。今回,粘弾性流体が示す変わった振る舞いをいろいろと紹介し、その性質を活用した事例等も紹介します。また、このような流体を対象とした流動解析は、数値不安定性の強い問題として知られています。3相接触点における特異点問題などにも触れながら紹介します.
第10回講演会 5月25日(火)15:10~
猿山 靖夫 氏 (京都工芸繊維大学高分子機能工学専攻)
温度変調法のスローダイナミクスへの応用
温度変調法は、平衡熱力学量である比熱の測定法として開発された実験技術であ
るが、動的現象の新しいタイプの実験技術として有効であることが、近年の研究
で明らかになってきた。これまでに、高分子結晶の融解および結晶化、ガラス転
移、有機結晶中の遅い運動などで興味深い結果が得られている。セミナーでは温
度変調法の基礎と応用例の説明を通して、その有効性を示したい。
第9回講演会 5月6日(木)15:10~
郡 宏 特任助教 (お茶大アカデミック・プロダクション,JSTさきがけ兼任)
リズムの科学
この世界には様々なリズムが存在します.例えば,メトロノームや振り子時計といった機械が作り出すリズムや,歩行や鼓動、活動と睡眠の繰り返し,ホタルの明滅といった生き物が持つリズムなどが挙げられます.また化学反応でもリズミカルに色が変わる反応が存在します.このようなリズムには2つの大きな特徴があります.リズムが固有のペースを刻む「自律性」と,リズムとリズムを合わせ合う「同期現象」です.これらは生物・医療・工学などの広い分野で重要な概念であり,また,物理学がその理解に大活躍できる話題です.この講義では,様々なムービー,少しの数式,最先端の研究の話題などを交えながらリズム現象の物理学について解説します.また,メトロノームや上述の化学反応を使ったびっくりするような実験をみなさんに直に体験してもらいます.
第8回講演会 3月8日(月)12:00~
藤江 遼 氏 (九州大学大学院)
自己組織化する階級社会
社会的な階級の自己組織化は、動物社会、人間社会に見られる普遍的な社会現象の一つである。
Bonabeauらにより、単純なランダム過程の帰結として階級社会の出現が示されて以来、階級社会の構造、発生のメカニズムを物理的視点から理解する研究が行われているが、その機構は未だ明らかにされていない。
私たちは、平等社会から階級社会への転移を示す階級形成モデルを提案し、モンテカルロ・シミュレーション、平均場による解析を行った。本講演では、階級社会の構造とその発生条件に対して、戦いに参加するためのコスト、相互作用ネットワークの構造、社会の傾向が与える影響について議論する。
第7回講演会 1月13日(水)15:10~
河津 璋 氏(東京理科大学)
走査トンネル顕微鏡法による表面研究
走査トンネル顕微鏡法(Scanning tunnneling microscopy:STM)は先端の鋭い探針と試料表面の間に流れるトンネル電流を測定しながら、探針を試料表面上で走査することにより、試料表面を 原子的分解能で観察し、その構造のみならず、電子状態に関する情報をも与えてくれる表面分析法である。
この測定法は、回折法のような平均的情報を与える測定法とは異なり、表面の個々の欠陥やクラスターなどの局所的構造の解明に対しても有効な方法である。
本講演においては、はじめにSTMの原理、装置についてふれ、実際にどのような情報が得られるかを具体例で示し、その有用性と問題点についても言及する。
第6回講演会 12月14日(月)15:10~
吉武 裕美子 助教 (東京電機大学 理工学部)
ゲルの表面波
濡れ性や吸着性を特徴づける表面張力は、薬剤の塗布や化粧など、生体物質の表面においても非常に重要なパラメータである。しかしゲルの表面張力は、その固体的性質により、吊り板法やペンダントドロップ法などの従来の表面張力測定では測定できない。現在、ゲル表面張力測定として表面波による手法に期待が寄せられているが、その特異な性質により困窮している。
本セミナーでは、最近の研究により明らかになったゲル表面波の伝搬特性、およびレーザー光を用いたゲルの表面張力、弾性率の新しい測定法について述べる。
第5回講演会 11月30日(月)15:10~
細田 真妃子 講師 (東京電機大学 理工学部)
球回転粘度計を用いた粘性測定
極微小量の試料容量で粘性を非接触測定できるEMS(Electro Magnetically Spinning)粘度計測システムを開発した。この装置により、流体の粘度曲線を迅速か つ正確に計測することができる。このシステムを用いてタンパク質水溶液の流動曲線 計測を試みた。タンパク質をはじめとする生体系材料は、一般に貴重で高価である一 方、その形態・機能を制御する温度、pH、濃度などのコントロールパラメータは多岐 にわたるため、微小量の試料について迅速にレオロジー的計測を実現するシステムの 開発が求められていた。今回の計測では特にその迅速性の確認、および過去のレオロ ジー的な研究結果との整合性の検討を行うことを目的としている。
第4回講演会 10月21日(水)15:10~
高須 昌子 教授 (東京薬科大学 生命科学部)
四面体型ゲルのシミュレーションによる研究
四面体型ゲルは東大の酒井先生らによって作成されており、
均一で強度が強いゲルとして、生体への応用の観点からも
注目されている。
我々はこの四面体型ゲルの粗視化したモデルを作成し、
ブラウニアンダイナミクス・シミュレーションを用いて
特にゲル化後の構造形成に関して研究を行っている。
構造を特徴付けるループ長の計算結果などを議論する。
第3回講演会 10月15日(木)15:10~
仲光 邦昭 准教授 (東京電機大学 物理学コース)
場の相互作用と非線形偏微分方程式
電磁場内を運動する非相対論的量子荷電粒子を記述する通常の シュレディンガー方程式は,ある指定された電磁場内の荷電粒 子の運動を記述するものであり,荷電粒子の運動により引き起 こされる周囲の電磁場の変化を無視している.実際には荷電粒 子の運動は周囲の電磁場を変化させ,この電磁場の変化は荷電 粒子の運動を変化させ,それがまた電磁場を変化させ...と いった現象が起こる.この状況はシュレディンガー方程式とマ ックスウェル方程式を組み合わせた非線形偏微分方程式系によ り記述される.ここではこの種の非線形方程式について解説す る.
第2回講演会 7月9日(木)15:45~
井上 真 准教授 (東京電機大学 物理学コース)
How magets become magnetized.
-- Eigenfunctions of the 2D Ising model --
磁石はいかにして磁石になるか。
ーー2次元 Ising 模型の転送行列固有関数ーー
The eigenfunctions of the transfer matrix are studied.
Coefficient of spin-state shows some interesting temperature dependences.
I will(may) show a simple easy 1D example in first half for beginners.
・2次元 :空間が2次元。
・Ising 模型:磁石の数学模型。磁石のS・N極をスピンの上向き・下向きで表す。
・転送行列:数学的に模型を解く方法。こいつをかけ算すると分配関数が求まる。
・固有関数:行列の固有関数
・スピン:電子の持つ量子力学的自由度のひとつ。
・分配関数:熱力学的諸量(比熱など)の母関数。
第1回講演会 6月4日(木)第4限 (15:10~)
木下 彬 教授 (東京電機大学 物理学コース)
熱力学におけるエントロピー増大則の導入法
Methods for introducing the Law of Increase of Entropy in Thermodynamics
It is shown that so called Clausius inequality
is not crucial to lead the law of increase of entropy with the Clausius method. Using
two traditional settings in thermodynamics, the law is reached without needing the inequality.
One method is to use Carnot cycles for compensations of heat in reservoirs, while
the other is to use the fact that the efficiency of an irreversible engine is lower than
that of Carnot engine.